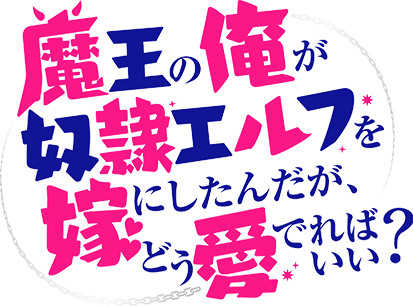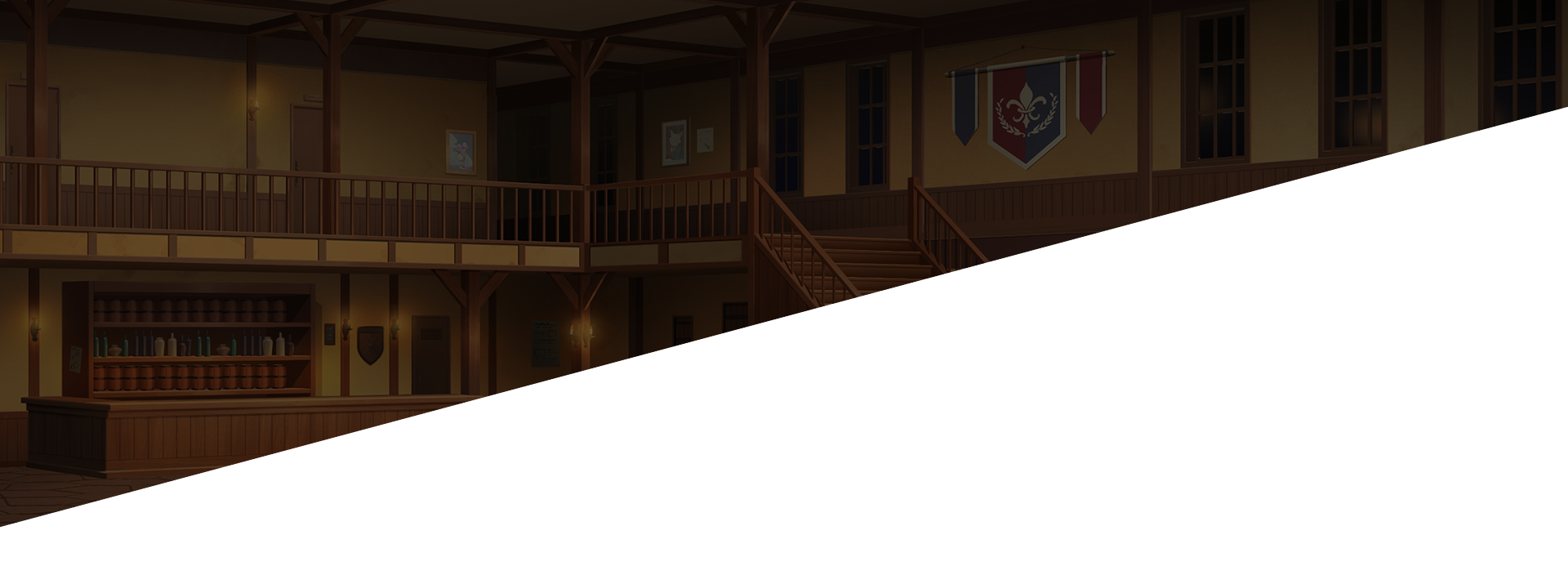ーValentine's Day Special Storyー
 NEXT
NEXT PREV
PREV
「チョコレートのお祭りですか?」
友人のシャスティルからの話に、ネフィとフォルは首を傾げた。
「うむ。祭りというものは街の活性化に繋がるから、教会としても力を入れてるんだ。それで今回はチョコレートを親しい相手に贈るという催しはどうかという話になって」
「へええ。チョコレートのプレゼントですか。素敵ですね」
チョコレートの作り方なら、先日もうひとりの友人のマニュエラから教えてもらった。
「ザガンさまも、喜んでくださるでしょうか?」
教会の祭りをザガンがどう受け取るかという問題はあるが、彼は美味しいものを食べると本当に少年のように喜んでくれる。
――そういうときのザガンさまは、本当に可愛いんです。
そんな姿に思いを馳せていると、フォルがスカートの裾を引っ張る。
「じゃあ、ネフィには私があげる」
「ふふ、ありがとうございます、フォル」
「ふたりが喜んでくれて、私も嬉しいよ。……と言っても、実は私もチョコレートというものをまだ食べたことがないんだがな」
得意げに語るシャスティルに、フォルが気の毒そうな瞳を向ける。
「しっぽ頭、チョコレートを食べたことない? 聖剣所持者なのに?」
「だ、だってチョコレートって高級品じゃないか。お給料はほとんど全部家に入れちゃってるし、うちの家もうボロボロだから維持費も馬鹿にならないというか……」
「可哀想……」
哀れみの眼差しに、シャスティルの目に屈辱の涙が浮かんだ。ネフィは話を変えるようにポンと手を叩く。
「そ、それで、わたしたちはなにをすればいいんでしょうか?」
「あ、うむ。新しいことを始めるにはなにかと課題も多くてな。前にもこういう案はあったのだが、そのときも上手くいかなかったらしい。だから――」
「――一度自分でも作って確かめてみようと……」
「「え」」
名案とばかりに明るい調子で言うシャスティルに、ネフィとフォルは露骨に顔を強張らせた。
「しっぽ頭はたぶん、勘違いをしている。魔術は万能ではない。毒物を美味しいお菓子に変えられるような魔術は存在しない」
きっと、フォルは精一杯言葉を選んだのだろう。だが、その優しさゆえにシャスティルの笑顔はガラスのように砕けることになる。
「フォル、言い過ぎですよ。シャスティルさんはただ、お料理の経験が少ないだけなんですから」
「じゃあ、ネフィはうちの厨房にしっぽ頭が立つの平気?」
「そ、それは……」
「ネフィまでっ?」
とうとうシャスティルが泣き崩れるが、ネフィにはかける言葉が見つからなかった。
「シ、シャスティルさん、泣かないでください。きっと、シャスティルさんにもできることがなにかあるはずです!」
チョコレートを作れるとは、言ってあげることができなかった。
「でも、しっぽ頭にできることなんて、本当にある?」
「えっと、型に流し込むことくらいなら誰でもできるじゃないですか?」
「……できる?」
「バ、バカにしないでくれ! それくらいは私にだってできるぞ」
「じゃあ、この型に水を注いでみて」
「よし、任せてくれ――ふぎゃんっ?」
型に水を入れるとかそれ以前に、シャスティルはヤカンを持ったまま派手にすっ転んだ。
「……すまない。私が愚かだった」
「しっぽ頭には難しすぎる。もっと簡単なことじゃないと」
「でも、これより簡単なことなんて……あ、そうだ!」
ネフィはペンと紙片を取り出す。
「シャスティルさんが形を考えるというのはどうでしょうか?」
「形? デザインをするということか?」
「はい。シャスティルさんが考えたデザインを、わたしたちが作るんです。きっと、街の人たちも喜びますよ」
「そ、そうか。やってみるよ、ネフィ!」
元気を取り戻したシャスティルは紙片にペンを走らせるが……。
「これは…………なに?」
フォルが名状しがたいとばかりに絶句する。無理もない。そこに描かれていたのは、なにやら角の生えたアンデッドのような不気味ななにかだった。ネフィにも理解できない。
「なにって、ウサギ以外のなにに見えるんだ?」
「そう……。今度、しっぽ頭に図鑑を貸してあげる。ウサギの絵も載ってるから」
「ウサギを見たことがないわけではないのだが?」
とはいえ、ウサギならネフィでも知っている。隠れ里での数少ない友達だったのだ。
「ひとまず、型に流し込むタイプの簡単なものを作ってみましょうか。あ、でもウサギの型はなかったような……」
「型 なら私が魔術で整えられる」
「ふふ、フォルは頼りになりますね」
「では溶かすのは私が――」
「シャスティルさんは、座っていてくださいね?」
「ひゃい!」
チョコレートはネフィが溶かし、フォルに形を整えてもらえばチョコレートは一刻ほどですぐ作ることができた。
「おお! これはなんとも可愛らしいな。やはりネフィはザガンにあげるのか?」
「はい、もちろん。シャスティルさんはどなたにチョコレートを贈られるのですか?」
シャスティルの手には、チョコレートの包みが四つ載せられていた。
「ああ、それなんだが……――はい、ネフィ。それにフォルも」
綺麗に包んだチョコレートを、シャスティルはネフィたちに手渡した。
「私の親しい友人といったら、あなたたちだからな」
「あうぅ。ありがとうございます」
「作ったの、私たちだけど」
突き放すような言葉を投げつつも、フォルもまんざらではなさそうに顔をほころばせていた。
「あとは、ザガンにも一応渡しておいてくれ。彼にも世話になっているからな」
「最後のひとつは?」
「バルバロスに渡そうと思って。先日、私が毒を盛られたときに助けてもらったらしいから。まあ、聖騎士からもらって喜ぶかは疑わしいとは思うが……」
「きっと、喜んでくださいますよ」
ネフィはそう言って励ますが、結局バルバロスは受け取らなかったらしい。数か月後に、それをひどく後悔したとかしなかったとか。
 SPECIAL TOP
SPECIAL TOP