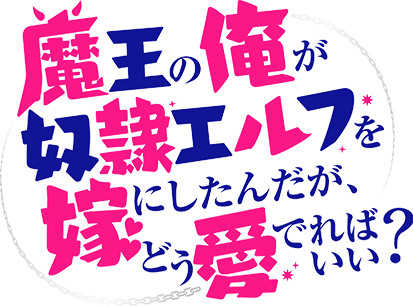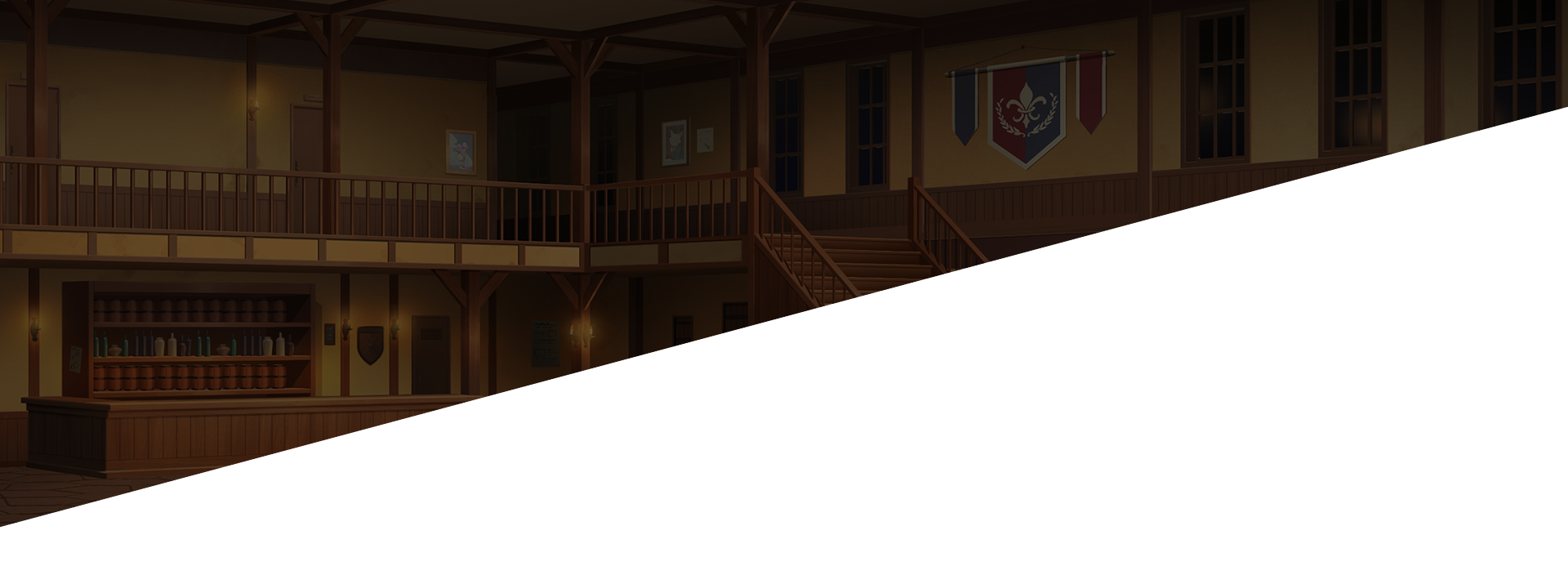ーGood Couple’s Day Special Storyー
 NEXT
NEXT PREV
PREV
「――キッチン『エルフの家』にようこそ!」
愛しい少女が笑顔で呼びかける。
――ネフィ、あんなふうに笑うんだな。あのボロ城を処分して本当によかった。
オークションで有り金全部はたいて彼女を落札したザガンは、当然のこと文無しで路頭に迷った。それゆえ、最後の財産である城を処分して軽食屋を開いたのだが、これが思いの外盛況して、いまでは街でも話題の店となっていた。
その店とネフィを守るのが、いまのザガンの使命である。
「ご主人さま。オーダー、オムライスをふたつです」
「うむ! 任せるがいい」
そう応えてフライパンを手に取り、ザガンは硬直する。
――あれ? オムライスって、どうやって作るんだ……? そもそも、オムライスとはどんな食べ物だ?
浮浪児時代、下水道に転がっていた腐りかけの肉を食って生死の境を彷徨って以来、火を通すとか日干しにするとかいう最低限の調理は学んだものの、それは美味しい料理を作れるかとは別の話である。
自分は用心棒だった気がするのだが、いつの間にか魔術師のローブではなくシェフのコックコートを着ている。
――えっと、まずは、調味料……? 味付けか?
だが、なにを入れるのが正解だ?
塩だろうか。砂糖だろうか。調理台には他にも胡椒だとかバジルだとか、用途不明の調味料が無数に陳列している。
――う、うおおおおっ、考えろ! せっかくネフィがここまで盛り上げてくれた店なのに、不味い飯を出すわけにはいかんのだ!
うろたえるザガンに、ネフィが首を傾げる。
「ご主人さま、どうなさいましたか?」
「あ、いや、その……。オムライスとは、どんな食べ物だったかと思ってだな」
呆けたおじいちゃんのようなことをつぶやくザガンに、ネフィは仕方なさそうに微笑む。
「ご主人さま、まずは卵をお割りください。中のライスはすでに用意されていますので」
「そ、そうか。さすがネフィだな」
「恐縮です」
だが、卵を手に取ってザガンはまた息を呑む。
――卵を、砕かずに割る……だと?
卵を割ったことがないわけではないのだが、最低の衛生環境で生活してきたザガンは卵は割っても殻ごと砕いて食べていた。綺麗に割るということを考えたことすらない。
そんなザガンの戸惑いを見越したように、ネフィはザガンに卵を握らせると、そっとその手に自分の手を重ねる。
「はうあっ」
「ご主人さまっ?」
勢い余って卵を握りつぶしてしまうザガンに、さすがのネフィも悲鳴を上げる。
――だ、だだだだって、ネフィの方から手を握ってきてくれるとは思わないだろう!
だが、オムライスを作らなければならないのだ。ザガンは気を取り直して頭を振る。
「す、すまん。取り乱した」
「いえ、卵は優しく持ってあげてくださいまし」
新しい卵を手に取ると、ネフィはそれを優しく流しの側面にコンコンとぶつける。すると表面に小さなヒビが入り、それをゆっくりと左右に開くよう誘導してくれる。
「お、おお……。綺麗に割れた」
「お上手ですよ、ご主人さま」
「ふ、ネフィの教え方が上手いからだ」
「そ、そうでしょうか……?」
愛しい少女はまんざらでもなさそうに微笑んだ。
それから卵を塩とミルクで味付けると、フライパンを火にかける。
「卵は強火で手早く焼いてあげてください。中が半熟のうちに形を作ってあげるのが大切です」
「うむ。やってみる」
だが、液体の卵をまとめるというのも素人には難しい話だ。するとネフィはそれもわかっていたように、背中越しにフライパンを握るザガンの手に手を重ねる。
――ほわわわわわっわわっ?
手を握られたことや背中から抱擁される形になったのもさることながら、自分の脇の間から愛しい少女が顔を覗かせているというのは衝撃的な可愛さで、ザガンは気を失いそうになった。
そのおかげで力が抜けたのか、ネフィにされるがままフライパンを傾け、器用に卵をくるりと引っくり返すことができた。
「おお! ネフィは魔術を使えたのか?」
「いえ、魔術を使わなくても練習すればできますよ?」
「そ、そうなのか」
――ふたりで台所に立って料理するって、なんか〝夫婦〟というものみたいだな……。
魔術師が夢想するには滑稽な話だが、ザガンはそう思った。
ともあれ、ネフィのおかげで卵は綺麗に焼くことができた。それを皿に載せると、ネフィがケチャップを使って綺麗に盛り付けてくれる。
「お待たせいたしました」
「ああ? マジで遅せえぞ。なにチンタラやってやがんだぶべらッ」
「なぜ俺とネフィが作ったオムライスを食べるのが貴様がなのだ!」
ネフィに対して悪態を付いている客の顔はなぜか悪友で、ザガンは反射的にぶん殴っていた。
「――ご主人さま、街に到着したようです」
「へあ?」
ネフィにそう声をかけられ、ザガンは目を覚ました。周囲を見渡してみると、そこはキッチン『エルフの家』ではなく、馬車の荷台である。
「あ、あれ……? 俺たちのキッチンは?」
「はい?」
不思議そうに小首を傾げる愛しい少女の姿に、ようやくザガンも意識がはっきりしてくる。
――そうだった。なんか道ばたに生えてた野盗を蹴散らしたら、金貨をもらった上に馬車で街まで送ってもらえることになったんだ。
昨晩、ネフィが来て初めての夜ということもあって緊張して一睡もできなかった。それもあって、馬車に揺られるうちに眠ってしまったらしい。
ザガンは馬車を降りると、ネフィに声をかける。
「ではネフィ、買い物に行くぞ」
「はい、ご主人さま」
ネフィはスカートの裾を持ち上げ、危なっかしい足取りで馬車を降りる。
ザガンはそれを支えようとは思ったものの、どうしたらいいかわからず中途半端に手を伸ばすだけに終わってしまった。
――なんで俺は手を握るくらいのこともしてやれないのか……。
夢の中では自然に手を取り合ったりしていたというのに。
自分の不甲斐なさに落胆しながらも、ふたりは並んで歩いていくのだった。
そんなふたりが真っ当な恋人になれるのは半年も先のことである。
 SPECIAL TOP
SPECIAL TOP